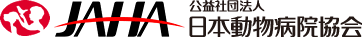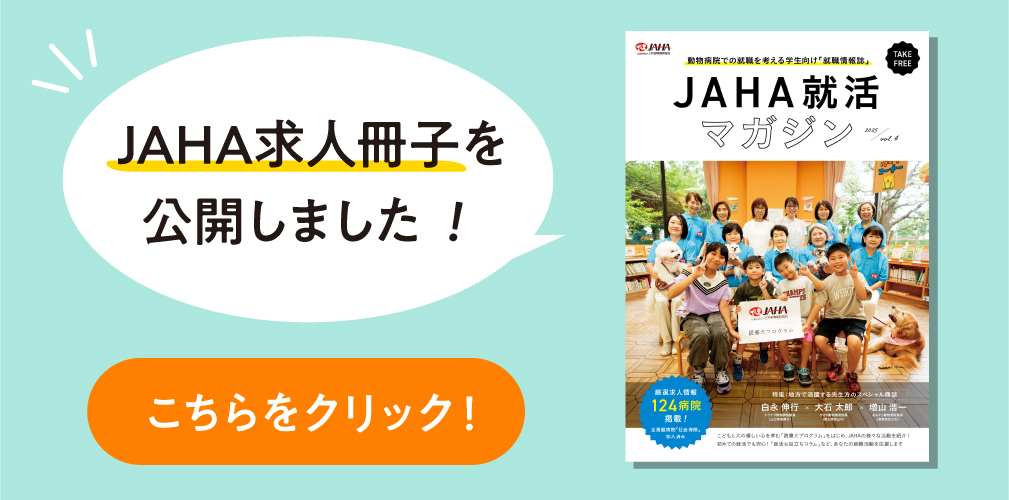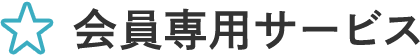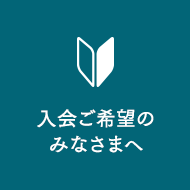<終了>第177回国際セミナー「“From Top to Bottom” 〜鼻から会陰まで〜」
「“From Top to Bottom” 〜鼻から会陰まで〜」
短頭種気道閉塞症候群〜肝胆系〜泌尿器系のよくある手術から最先端の手技、さらにマイクロサージェリーまで盛り沢山の3日間
後援
(一社)日本獣医麻酔外科学会、日本獣医腎泌尿器学会、(公社)東京都獣医師会、(公社)神奈川県獣医師会、(公社)千葉県獣医師会、(公社)埼玉県獣医師会、(公社)川崎市獣医師会、(公社)横浜市獣医師会、(公社)大阪府獣医師会、(公社)大阪市獣医師会、(一社)兵庫県獣医師会、(公社)京都府獣医師会、(公社)京都市獣医師会

講師
Dr. Heidi Phillips
Diplomate American College of Veterinary Surgeon
Associate Professor, University of Illinois
Diplomate American College of Veterinary Surgeon
Associate Professor, University of Illinois
ご案内
Dr. Phillipsは米国の獣医外科専門医の中で現在最も勢いのある外科医の1人です。
「BOAS(短頭種気道閉塞症候群)と言ったらDr. Phillips」と言っても過言ではないほど、犬と猫における本疾患の病態把握や治療の発展に尽力されており、LATE(レーザー補助下鼻甲介切除術)など、BOASに対して数種類の最新の外科手技を実施している数少ない外科専門医の1人です。
更にマイクロサージェリーでも世界的に著名で、彼女が自らデザインしたマイクロサージェリーのトレーニングコースは、獣医師だけでなく医師が参加するほど大変人気です。
1日目は、犬と猫におけるBOASの病態・検査法から治療法に関して詳しく触れる中で、LATEを始めとする複数の新しい外科手技に関して画像を多く活用してレクチャーして頂きます。
2日目は、Dr. Phillipsの得意分野の1つである肝胆膵系疾患に対する外科治療に関して取り上げ、特に様々な疾患に対する肝外胆管系の手術手技について詳しくお話しして頂きます。
3日目の泌尿器系の一般外科とマイクロサージェリーでは、尿管・前立腺・尿道などの外科手技を多く紹介していただきます。
今を輝くDr. Phillipsから3日間たっぷりと学べる機会は大変貴重ですので、今回取り上げるトピックスを勉強中の先生方から既に手術経験の豊富な先生方まで、多くの方に是非ともご参加頂けますと幸いです。
学術委員 篠田 仁美(近江八幡動物医療センター 森動物病院)
「BOAS(短頭種気道閉塞症候群)と言ったらDr. Phillips」と言っても過言ではないほど、犬と猫における本疾患の病態把握や治療の発展に尽力されており、LATE(レーザー補助下鼻甲介切除術)など、BOASに対して数種類の最新の外科手技を実施している数少ない外科専門医の1人です。
更にマイクロサージェリーでも世界的に著名で、彼女が自らデザインしたマイクロサージェリーのトレーニングコースは、獣医師だけでなく医師が参加するほど大変人気です。
1日目は、犬と猫におけるBOASの病態・検査法から治療法に関して詳しく触れる中で、LATEを始めとする複数の新しい外科手技に関して画像を多く活用してレクチャーして頂きます。
2日目は、Dr. Phillipsの得意分野の1つである肝胆膵系疾患に対する外科治療に関して取り上げ、特に様々な疾患に対する肝外胆管系の手術手技について詳しくお話しして頂きます。
3日目の泌尿器系の一般外科とマイクロサージェリーでは、尿管・前立腺・尿道などの外科手技を多く紹介していただきます。
今を輝くDr. Phillipsから3日間たっぷりと学べる機会は大変貴重ですので、今回取り上げるトピックスを勉強中の先生方から既に手術経験の豊富な先生方まで、多くの方に是非ともご参加頂けますと幸いです。
学術委員 篠田 仁美(近江八幡動物医療センター 森動物病院)
トピックス
Day 1 13:00 -19:00
短頭種気道閉塞症候群(BOAS)
この講義シリーズでは、従来の上気道手術と、最新の複数箇所における上気道手術の手技や手術成績の比較に焦点を当てる。最新の手術手技には短頭種の犬と猫における鼻翼鼻前庭形成術(ala vestibuloplasty)や、犬における折りたたみ式口蓋形成術(folded flap palatoplasty)、レーザー補助下鼻甲介切除術(LATE)などを挙げる。Dr. Phillipsは短頭種の複数部位の上気道閉塞に対し、最新の治療法としてそれらの手術を組み合わせて行った豊富な経験を持つ、世界で3人しかいない外科医の1人であり、その専門知識を本セミナーで共有する。参加者は高品質な写真や動画を通して、従来の手術と最新の手術の手技を学ぶ。
特に注目する内容:
・ 患者の包括的な評価-ヒストリー、身体検査、運動耐性試験とBOASの重症度評価、高度画像検査(CT)の活用法
・ 鼻鏡検査および喉頭鏡検査、ドキサプラムを用いた喉頭検査
・ 従来の術式と最新の術式の比較(鼻翼鼻前庭形成術、折りたたみ式口蓋形成術、扁桃切除術、喉頭嚢切除術、LATE)
・ 巨舌症に対する外科的選択肢-舌切除術に関する研究
・ 猫の短頭種症候群-症状、臨床的予後、治療法
・ 麻酔および手術の合併症
この講義シリーズでは、従来の上気道手術と、最新の複数箇所における上気道手術の手技や手術成績の比較に焦点を当てる。最新の手術手技には短頭種の犬と猫における鼻翼鼻前庭形成術(ala vestibuloplasty)や、犬における折りたたみ式口蓋形成術(folded flap palatoplasty)、レーザー補助下鼻甲介切除術(LATE)などを挙げる。Dr. Phillipsは短頭種の複数部位の上気道閉塞に対し、最新の治療法としてそれらの手術を組み合わせて行った豊富な経験を持つ、世界で3人しかいない外科医の1人であり、その専門知識を本セミナーで共有する。参加者は高品質な写真や動画を通して、従来の手術と最新の手術の手技を学ぶ。
特に注目する内容:
・ 患者の包括的な評価-ヒストリー、身体検査、運動耐性試験とBOASの重症度評価、高度画像検査(CT)の活用法
・ 鼻鏡検査および喉頭鏡検査、ドキサプラムを用いた喉頭検査
・ 従来の術式と最新の術式の比較(鼻翼鼻前庭形成術、折りたたみ式口蓋形成術、扁桃切除術、喉頭嚢切除術、LATE)
・ 巨舌症に対する外科的選択肢-舌切除術に関する研究
・ 猫の短頭種症候群-症状、臨床的予後、治療法
・ 麻酔および手術の合併症
Day 2 10:00 -17:00
肝胆道外科
この講義シリーズでは、複雑な肝胆道系の解剖学、生理学、および外科的疾患の病態生理に焦点を当てる。参加者は、胆道系全域にわたる疾患の兆候を評価する方法や、術中の判断に苦慮した際に治療方針の決定に役立つアルゴリズムを学ぶ。また、胆道疾患のある動物を手術に備えて安定させる方法、術中の懸念事項を認識し治療する方法、さらに最先端のケアを提供するための術後のモニタリングおよびサポート法についても学ぶ。
講義には以下の処置および手技を含む:
・ 胆嚢粘液嚢腫、梗塞や腫瘍などの胆嚢壁疾患に対する胆嚢摘出術
・ 胆嚢管および総胆管の逆行性と順行性カテーテル挿入法の比較
・ 胆石症の治療法:
・ 胆嚢切開術
・ 総胆管切開術
・ 括約筋切開術
・ 胆道ステント留置術
・ 胆嚢迂回術:
・ 胆嚢十二指腸吻合術
・胆嚢空腸吻合術
この講義シリーズでは、複雑な肝胆道系の解剖学、生理学、および外科的疾患の病態生理に焦点を当てる。参加者は、胆道系全域にわたる疾患の兆候を評価する方法や、術中の判断に苦慮した際に治療方針の決定に役立つアルゴリズムを学ぶ。また、胆道疾患のある動物を手術に備えて安定させる方法、術中の懸念事項を認識し治療する方法、さらに最先端のケアを提供するための術後のモニタリングおよびサポート法についても学ぶ。
講義には以下の処置および手技を含む:
・ 胆嚢粘液嚢腫、梗塞や腫瘍などの胆嚢壁疾患に対する胆嚢摘出術
・ 胆嚢管および総胆管の逆行性と順行性カテーテル挿入法の比較
・ 胆石症の治療法:
・ 胆嚢切開術
・ 総胆管切開術
・ 括約筋切開術
・ 胆道ステント留置術
・ 胆嚢迂回術:
・ 胆嚢十二指腸吻合術
・胆嚢空腸吻合術
Day 3 10:00 -17:00
獣医外科におけるマイクロサージェリーの活用
Dr. Phillipsは、ペンシルバニア大学で40例以上の猫の腎移植手術を経験し、マイクロサージェリーの技術を習得した。その後、クリーブランド・クリニックおよびコロンビア大学でさらに経験を積み、イリノイ大学にMicrosurgery Research and Training Laboratoryを設立し、尿管閉塞の新しいマイクロサージェリーモデルを開発した。米国獣医外科学会の年次学会では「尿管閉塞への包括的アプローチ」実習の座長を務め、また獣医学におけるマイクロサージェリーについて国際的に講演を行っている。
この講義シリーズでは、Dr. Phillipsの専門知識を活かし、手術用ルーペ、カールストルツ社のVITOMシステム、手術用顕微鏡などの、最も一般的な拡大補助器具の適切な使用方法と活用に焦点を当てる。参加者は、これらの拡大補助器具の適切な使用方法とそれぞれの器具を使用する場面や、拡大補助器具を用いて上部および下部尿路のさまざまな手術を成功させる方法も学ぶ。
講義には以下の具体的な処置を含む:
・犬と猫の尿管手術
・尿管切開術
・新尿管膀胱吻合術
・膀胱内粘膜縫合法
・膀胱外法
・新尿管造瘻術
・尿管の端端吻合および側側吻合
・部分的および完全前立腺摘出術
・尿道膀胱吻合術
・尿道吻合術
・猫の会陰尿道造瘻術
・犬の陰嚢尿道造瘻術
・尿道脱出
Dr. Phillipsは、ペンシルバニア大学で40例以上の猫の腎移植手術を経験し、マイクロサージェリーの技術を習得した。その後、クリーブランド・クリニックおよびコロンビア大学でさらに経験を積み、イリノイ大学にMicrosurgery Research and Training Laboratoryを設立し、尿管閉塞の新しいマイクロサージェリーモデルを開発した。米国獣医外科学会の年次学会では「尿管閉塞への包括的アプローチ」実習の座長を務め、また獣医学におけるマイクロサージェリーについて国際的に講演を行っている。
この講義シリーズでは、Dr. Phillipsの専門知識を活かし、手術用ルーペ、カールストルツ社のVITOMシステム、手術用顕微鏡などの、最も一般的な拡大補助器具の適切な使用方法と活用に焦点を当てる。参加者は、これらの拡大補助器具の適切な使用方法とそれぞれの器具を使用する場面や、拡大補助器具を用いて上部および下部尿路のさまざまな手術を成功させる方法も学ぶ。
講義には以下の具体的な処置を含む:
・犬と猫の尿管手術
・尿管切開術
・新尿管膀胱吻合術
・膀胱内粘膜縫合法
・膀胱外法
・新尿管造瘻術
・尿管の端端吻合および側側吻合
・部分的および完全前立腺摘出術
・尿道膀胱吻合術
・尿道吻合術
・猫の会陰尿道造瘻術
・犬の陰嚢尿道造瘻術
・尿道脱出
日程・会場
参加費・お申し込み
参加費と講義資料代(税込)
※セミナー参加費には、講義資料代は含まれておりません。
| 参加区分 | JAHA会員料金 | 一般料金/会員当日料金 | |
| 3日間受講 ※資料なし |
獣医師 | 66,000円 | 72,600円 |
| 獣医師奨学制度 | 33,000円 | - | |
| 学術会員 | 19,800円 | - | |
| 学生A(獣医師免許なし) | 9,900円 | 13,200円 | |
| 学生B(獣医師免許あり) | 19,800円 | 26,400円 | |
| 単回受講 ※資料なし |
獣医師 | 22,000円 | 24,200円 |
| 獣医奨学制度 | 11,000円 | - | |
| 学術会員 | 6,600円 | - | |
| 学生A(獣医師免許なし) | 3,300円 | 4,400円 | |
| 学生B(獣医師免許あり) | 6,600円 | 8,800円 | |
| 講義資料 (3日分) |
データ(PDF)のみ 6,600円 | ||
| データ(PDF)+冊子セット 8,800円 | |||
| 昼食 | 1,540円/1日 ※10時開始のセミナーのみ | ||
※申込者と参加者が異なる場合は、備考欄に参加者名をご記入ください。
講義資料について
【データ(PDFファイル)】
○講演スライドと講義ノートが含まれます。
○購入された方には、3月3日(月)に資料ダウンロード先をご案内いたします。
【冊子】
○講演スライドのみ(講義ノートは含まれません)カラー印刷したものを、当日会場でお渡しいたします。
*冊子のみの販売は承っておりません。購入をご希望の方は、必ずデータとセットでご購入ください。
*追加で冊子をご購入の場合は1冊 2,200円となります。
○講演スライドと講義ノートが含まれます。
○購入された方には、3月3日(月)に資料ダウンロード先をご案内いたします。
【冊子】
○講演スライドのみ(講義ノートは含まれません)カラー印刷したものを、当日会場でお渡しいたします。
*冊子のみの販売は承っておりません。購入をご希望の方は、必ずデータとセットでご購入ください。
*追加で冊子をご購入の場合は1冊 2,200円となります。
優待区分での参加について
○「奨学制度」は、獣医師免許取得後3年目までのJAHA会員が対象【要事前申込】
○ 後援団体会員、日本獣医師会会員の方は、JAHA会員料金でご参加いただけます。申込み時、備考欄に所属団体名をご記入ください。
○「学生A」料金は「獣医師免許を持たない方」のみ対象。別途、学生証のコピーをご提出いただきます。
○「学生B」料金は「獣医師免許を取得済みの方」(主に社会人大学院生)が対象で、上長にあたる方の推薦状のご提出が必須となります。
○ 後援団体会員、日本獣医師会会員の方は、JAHA会員料金でご参加いただけます。申込み時、備考欄に所属団体名をご記入ください。
○「学生A」料金は「獣医師免許を持たない方」のみ対象。別途、学生証のコピーをご提出いただきます。
○「学生B」料金は「獣医師免許を取得済みの方」(主に社会人大学院生)が対象で、上長にあたる方の推薦状のご提出が必須となります。
申込
キャンセル規定
セミナー前日までにご連絡の場合:キャンセル料1,000円
・連絡日が事務局の休日にあたる場合は、留守番電話メッセージ、E-mailでご連絡をお受けします。
・講義資料のご案内後は、資料代のご返金は出来かねます。
・セミナー直前でキャンセルをされた場合、昼食代をご返金できない場合があります。
・講師が体調不良の場合、講演がキャンセルになる可能性もあります。その際は参加費をご返金いたします。キャンセル料はいただきません。
・連絡日が事務局の休日にあたる場合は、留守番電話メッセージ、E-mailでご連絡をお受けします。
・講義資料のご案内後は、資料代のご返金は出来かねます。
・セミナー直前でキャンセルをされた場合、昼食代をご返金できない場合があります。
・講師が体調不良の場合、講演がキャンセルになる可能性もあります。その際は参加費をご返金いたします。キャンセル料はいただきません。
ご連絡
・お申込後、申込確認書の送付などE-mailでご連絡しますので、事務局からのメールを受け取れるよう設定をお願い致します。
・当日会場にて直接お申込みの場合は、会員料金や優待料金の適応外となり、全て一般料金となります。
・事前に昼食をご注文されていない方、当日申込の方は各自で昼食をご用意ください。
・受付は講義開始の30分前から開始となります。開場は1時間前からです。
・会場にてビデオやデジカメでの撮影はご遠慮ください。講義の録音は可能です。
・会場では空調調整を行うよう努めますが、適温には個人差がありますので、温度調整できる服装でご来場願います。
・体調が優れない方、発熱等症状がある方はご来場をお控えください。
・当日会場にて直接お申込みの場合は、会員料金や優待料金の適応外となり、全て一般料金となります。
・事前に昼食をご注文されていない方、当日申込の方は各自で昼食をご用意ください。
・受付は講義開始の30分前から開始となります。開場は1時間前からです。
・会場にてビデオやデジカメでの撮影はご遠慮ください。講義の録音は可能です。
・会場では空調調整を行うよう努めますが、適温には個人差がありますので、温度調整できる服装でご来場願います。
・体調が優れない方、発熱等症状がある方はご来場をお控えください。